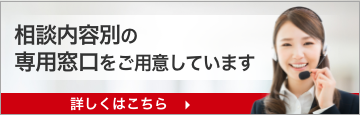研修は残業にあたるのか?|研修と残業の関係性を解説
- 労働問題
- 研修
- 残業

従業員のスキルアップを目的として、さまざまな研修プログラムを提供する会社も増えてきています。勤務時間内に研修が終了すればよいですが、長時間の研修であれば勤務時間をオーバーしてしまうこともあります。このような場合には、勤務時間を超えた部分については残業代を支払うべきだといえます。
労働時間を正確に把握して管理することは、企業の労務管理における重要な課題のひとつです。企業の経営者や担当者は、研修と残業との関係をしっかりと理解しておくようにしましょう。
本コラムでは、研修は残業にあたるのかについて、ベリーベスト法律事務所 木更津オフィスの弁護士が解説します。
1、研修の目的や内容によって残業にあたるかどうかが決まる
まずは、会社が実施する研修が就業時間を超えて行われた場合には残業にあたるのかどうかについて解説します。
-
(1)研修が残業にあたるかどうかの判断基準
企業によっては、従業員のスキルアップや業務に必要な知識の習得のために、研修プログラムを提供することがあります。
従業員全員の参加が義務付けられているものもあれば自由参加でよいというものまで、条件は研修内容によってさまざまです。
このような研修が残業にあたるかどうかは研修の目的や内容によって異なってくるため、ケースバイケースで判断していく必要があります。
具体的には、以下のような要素を踏まえて判断していきましょう。- 会社による明示の指示があるか:明示の指示があれば残業にあたる可能性が高くなります。
- 業務時間内に行われたか:業務時間内の研修だと業務の一環と判断され、残業にあたる可能性が高くなります。
- 会社が費用負担をしているか:研修費用を会社が負担していると業務の一環と判断され、残業にあたる可能性が高くなります。
- 参加が強制されているか:研修への参加が強制されている場合には、残業にあたる可能性が高くなります。
- 業務との関連性が高いか:業務との関連性の高い研修であれば、残業にあたる可能性が高くなります。
-
(2)残業にあたる研修と残業にあたらない研修の具体例
① 残業にあたる研修
残業にあたる可能性の高い研修としては、以下のようなものが挙げられます。- 従業員が全員参加することを義務付けられている研修
- 研修の内容について後日レポートなどの提出が義務付けられている研修
- 研修を受けなければ、業務に必要な知識が得られず、業務に支障が生じるような研修
- 研修は任意とされていても、不参加者への指導が予定されている研修
② 残業にあたらない研修
残業にあたらない可能性の高い研修としては、以下のようなものが挙げられます。- ヨガ、英会話など趣味に近い研修
- 従業員の有志で企画した研修
- 会社の施設を利用せず、従業員が費用負担して受講する研修
- 人事評価などに特に影響が及ぶことがない研修
2、そもそも労働時間とはどのような時間か
以下では、法律における「労働時間」の概要を解説します。
-
(1)労働時間とは
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下で働く時間のことです。
労働時間に該当する場合には、使用者は、労働者に対して賃金の支払いをしなければいけません。
つまり、研修も労働時間に含まれる場合には、賃金の支払い義務があるのです。
また、労働時間には「法定労働時間」と「所定労働時間」とに大きく分けられます。① 法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法により定められている労働時間です。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定められており、原則としてこの時間を超えて労働者を働かせることはできないとされています。
法定労働時間を超えて労働者を働かせるためには、労働者の代表者と使用者の間で36協定を締結して、それを所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
② 所定労働時間
所定労働時間とは、会社により定められた労働時間です。
就業規則や労働契約では始業時間と終業時間が定められており、始業から終業までの時間から休憩時間を除外したものが所定労働時間にあたります。
たとえば、始業時間9時、終業時間18時、休憩時間1時間という会社では、所定労働時間は8時間となるのです。 -
(2)法定労働時間を超えて働かせた場合には割増賃金の支払いが必要
所定労働時間を超えていたとしても、法定労働時間の範囲内の残業であれば、割増賃金の支払いは必要ありません(ただし、所定労働時間を超え法定労働時間を超えない分についても、通常の(割増しのない)賃金の支払いは必要になります)。
しかし、法定労働時間を超えて労働者に残業をさせた場合には、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になるのです。
なお、割増賃金の割増率は以下のように定められています。- 時間外労働……25%以上
- 深夜労働……25%以上
- 休日労働……35%以上
- 月60時間を超える時間外労働……50%以上
3、残業時間とされる、そのほかの例
研修のほかにも、以下のような時間は残業時間にあたる可能性があります。
-
(1)着替え時間
会社によっては、業務の開始または終了のタイミングで着替えが必要になる場合があります。
このような着替え時間も会社から着替えを義務付けられている場合には、残業時間にあたる可能性があります。
仕事をする際には制服の着用が義務付けられている会社では、制服に着替えなければ業務を行うことができませんので、明示的な指示がなかったとしても残業時間に含まれるのです。 -
(2)待機時間
具体的な作業を行っていなくても、使用者からの指示があればすぐに作業を行えるよう準備している時間のことを「待機時間」といいます。
待機時間を休憩時間と扱って残業代の支払いをしない会社も存在しますが、そのような対応は厳密にいえば違法です。
休憩時間は、あくまで労働から完全に解放された時間のことをいいます。
すぐに作業に移れるように待機している時間は、休憩時間とはいえません。
したがって、待機時間も残業時間に含まれるのです。
また、休憩中に来客や電話があった場合の対応を指示されていた場合にも、その時間は休憩時間ではなく待機時間といえるでしょう。 -
(3)始業前の朝礼
始業前に朝礼やミーティングを行う場合、このような朝礼やミーティングも会社が参加を強制させているものであれば、残業時間といえます。
また、明示的に強制をしていなかったとしても、朝礼やミーティングに参加しないことで何らかの不利益が生じる場合には事実上強制しているといえるため、これも残業時間に含まれるのです。
参加の有無が完全に労働者の自由に委ねられているものに限って、残業時間から除外することができます。
4、労働問題で弁護士ができること
労働問題でお困りの経営者の方は、弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)労働問題が行ったときに代理人として対応できる
労働者との間で、不当解雇や未払い残業代などのトラブルが生じた場合には、まずは、労働者との話し合いにより解決を図ることになります。
しかし、法的なトラブル対応に不慣れな方では、労働者対応に多くの時間を割かれてしまい、本業がおろそかになってしまうこともあります。
また、労働者から理不尽な要求をされ続けると精神的にも大きなストレスとなるでしょう。
弁護士であれば、会社の代理人として労働者への対応を行うことができるため、労働者対応が負担に感じるときは、弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士が法的観点から会社の処分や対応の正当性を主張していくことで、話し合いによる円満な解決が期待できます。
また、話し合いで解決できなかったとしても、弁護士には労働審判や訴訟などの対応も任せることができます。 -
(2)顧問弁護士であれば日常的なチェックによりトラブルを防止できる
顧問弁護士という形で弁護士を利用することで、企業は労働者との間のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
企業によっては就業規則を定めていたとしても、作成時から時間がたっており、現在の法制度との間に齟齬(そご)が生じていることもあります。
そのような場合には、顧問弁護士が就業規則を見直すことで、会社に発生するリスクを軽減することができます。
また、実際に労働者とのトラブルが生じたとしても、顧問弁護士であれば、問題の解決に向けた対応に迅速に着手することができます。
さらに、契約書などのリーガルチェック、コンプライアンス研修なども顧問弁護士に依頼することができるのです。
顧問弁護士を利用するにあたっては、費用が生じますが、法務部を新たに設けるよりもコストを抑えることができますので、法務機能のアウトソースとして利用してみることも検討してください。
5、まとめ
企業が労働者に対して提供している研修プログラムは、その内容や目的によっては、労働時間に含まれます。
したがって、終業時間を超えて研修が行われていた場合には、労働者に対して残業代の支払いが必要になる可能性もあるのです。
労働時間に含まれる研修であるにもかかわらず、残業代や賃金の支払いをしていないと、未払い賃金をめぐるトラブルが生じるおそれがあります。
トラブルを未然に予防するためや、発生してしまったトラブルに適切に対処するためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
企業の経営者や担当者の方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|